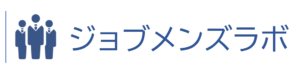Last Updated on 2020年10月11日 by ジョブメンズラボ
こんにちは。しんちゃんです。
新型コロナウイルス問題も一時よりは騒がれなくなりましたが、いまだに予断は許さない状況ですね。
コロナの影響により、この半年ほどで家計や事業に大きな影響を受けた方も少なくないと思います。
一方で、家計や事業への経済的な影響を軽減するために様々な支援策も打たれています。
今回は、新型コロナウイルス禍における【個人・世帯向け】の生活・経済支援制度について主なものをピックアップしてまとめてみました!
※情報は2020年9月時点のものです。
記事の内容
・コロナ禍における家計や事業を支援する制度は色々と整備されている
・個人向けとしては、話題になった10万円の特別定額給付金の他に「社会保険の納付猶予」、「小口資金/支援資金」、「住居確保給付金」、「奨学金」などが支援制度としてある!
本記事はこんな人におすすめ
・コロナ禍における支援制度で個人・世帯の家計に関係あるものを大まかに知りたい方
コロナ禍における生活・経済支援制度

新型コロナウイルスの影響を受けて施行された、もしくは拡大された制度(個人・世帯向け)は主に以下のようなものがあります。
【個人・世帯向けの生活・経済支援制度】
①「社会保険料等の納付猶予」
②「緊急小口資金・総合支援資金」
③「住居確保給付金」
④「奨学金(給付型・貸与型)

自身で活用できる制度があるかもしれませんし、今後何かあったときのために知っておきたいですね。これらの制度の概要を解説していきます!
社会保険料の納付猶予
コロナの影響により社会保険料などの納付が困難となった人への支援策です。
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等が対象になります。
社会保険料のほか、国税や公共料金等の支払・納付の猶予も認められる場合があります。
猶予が認められるものは以下になります。
| 項目 | 問い合わせ先 |
| 厚生年金保険料など | 管轄の年金事務所 |
| 国民年金 | 市区町村の国民年金担当課や年金事務所 |
| 国民健康保険 | 市区町村の国民健康保険担当課 |
| 後期高齢者医療制度の保険料 | 市区町村の後期高齢者医療担当課 |
| 介護保険料 | 市区町村の介護保険担当課 |
| 国税 | 国税庁 |
| 地方税 | 納付先の都道府県・市区町村の担当窓口 |

国民健康保険については、コロナの影響により一定の収入低下がある場合に減免が認められることもありますよ!
緊急小口資金・総合支援資金
「緊急小口資金」は休業などで一時的な資金が必要な方に10万円ないし20万円以内の特例貸し付けを行う制度です。
対象者は「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯」になります。
また、失業などで生活の立て直しが必要な世帯については「総合支援資金(生活支援費)」による貸し付けが受けられます。
こちらの対象者は「新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯」になります。
それぞれの概要は以下の通りです。
| 項目 | 措置期間 | 償還期限 | 貸付利子・保証人 | 貸付内容 |
| 緊急小口資金 | 1年以内 | 2年以内 | 無利子・不要 | 10万円以内もしくは20万円以内(世帯の状況によって上限額が20万円以内になります) |
| 総合支援資金 | 1年以内 | 10年以内 | 無利子・不要 | (二人以上世帯)月20万円以内 (単身世帯)月15万円以内 貸付期間:原則3月以内 |
詳細は厚労省生活支援特設ホームページで確認できます。

収入の減少については「収入の減少状況に関する申立書」に記載することで証明できます。給与明細等などは不要です!
住居確保給付金
住居確保給付金は「離職・廃業後2年以内である場合 もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合」に国や自治体が家賃相当額を支給する制度です。
これまでは離職・廃業した方が対象でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業により収入低下した方等も支給対象となりました。
市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。
世帯収入や世帯の預貯金額が要件になっているので、気になる方は厚労省生活支援特設ホームページで確認できます。
私の職場でも「マンションの隣の住民が転居していった」というような話を現実にちらほら耳にします。
住宅は生活の要ですから、是非支援してほしいですよね。

ちなみに支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われることになります!
奨学金(給付型・貸与型)
家計が急変した学生に向けて、給付型と貸与型の奨学金が設けられています。
対象は短期大学・大学・大学院・専修学校(専門課程)、高等専門学校に通う学生です。
給付型の所得基準は、住民税非課税世帯です。
こちらの制度は日本学生支援機構のホームページから詳細が確認できますが、まずは通っている学校の学生課に電話で相談をしてみた方が良いかもしれませんね。
まとめ

今回は、新型コロナウイルス禍における個人向けの生活・経済支援制度について主なものをまとめてみました。
様々な支援策が打たれていることは知っていても、なかなか自身が知っておくべき制度を見つけるのは簡単ではないと思います。
もちろん制度を使わずに生活できることが望ましいのですが、この先の「もしも」のためのセーフティネットとして、知っておいて損はないと思います。
自身だけでなく、周囲で支援が必要な方がいた際にはこういった情報を参考にしてもらえれば幸いです!