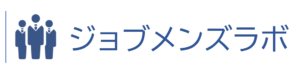Last Updated on 2021年1月29日 by ジョブメンズラボ
こんにちは!1歳の娘が新しく覚えたビンタを毎日浴びせられるよっすーです。
昨今、ホワイトワーカーと呼ばれる人の多くはコロナ禍で在宅勤務を経験し、「どこに住むか」「どんな家に住むか」を考えるきっかけになっていませんか?
そんな環境下、MBA取得の私は歩いて会社に通える場所から移り住む事を考えていません!
その理由、つまり「私が都内に住み、職住近接を選ぶ理由」を紹介します(^^)/
本記事の内容
- コロナ禍、コロナ後というものの、社会は劇的には変わらない
- 30代は人とのネットワーク、子供の教育があり都内に住むべき
- 地方に住むことのデメリットも良く考えよう
この記事をおススメする方
- コロナの影響でどこに住もうかなと悩み始めた方
- 地方移住を考えている方
私が職住近接を選択する理由
社会は劇的に変わりますか?

まず、私は「社会全体の生活様式は劇的には変わらない」という立場をとっています。
これは今までの生活に戻ろうとする、続けようとする慣性が強く働いている事を感じているためです。
わかりやすい例では「通勤電車」です。
6月15日時点で朝ラッシュ時の主なターミナル駅の自動改札出場者数は、感染拡大以前と比べて首都圏は62%、関西圏は75%まで戻っているという報道があります。
奥さま(あえて敬称)は電車で通勤していますが緊急事態宣言下で減った乗車率も緊急事態宣言以降は元に戻ったと聞いています。
多くの人が元通りを好みます。
その他には「ジョブディスクリプションが明確でない雇用と仕事の仕組み(阿吽の呼吸で進める日本企業の仕事の方法ともいう)」「Go to travelやGo to eatへの需要」「夜の街のおっさん」を見ていると思います。
よくメディアでは少数派を取材し「オフィスはもういらない!」「新しい働き方」と報道しますが、果たしてそのような方は全体の何割でしょうか。
特に、そもそもリモートワークという働き方に向き・不向きな職種があります。その点をすっ飛ばして「これこそ新しい働き方!」みたいな言説はポジショントークだと思っています。
緊急事態宣言下、各々が様々な試行錯誤をしたと思いますが、肌感覚で、元に戻ろうとする力が強いなと感じます。
従って、私はこのコロナの影響は、今すぐ地方移住を選択する理由にはならないと考えています。

もちろん、劇的に変わらないだけであって、変化は加速しており、5年~10年かけてゆっくり変わっていくのだろうと思っています。
30代は人的資本の蓄積を行うフェーズにある

我々30代は「資本蓄積」を行うステージであると考えています。
20代は「苦労は払ってでも買え」「石の上にも三年」というように、とにかく最初に入社した会社で与えられた業務にがむしゃらに物事と向き合うことによって、「何かきっと役に立つ」と考えてもよい時期であったかもしれません(ちなみに私は20代からこの考えは捨てるべきと考えていますが)。
しかし、30代はより戦略的に「蓄積」を考えるべきです。
理由は二つです。
同じ会社で残り続けるにしても、転職を考えるにしても、明らかに選択肢が減っていかざるを得ないこと、そして一般的に家族を持つ、子供を授かるなどのライフステージの変化が大きい事があります。
では30代の私たちが「戦略的に蓄積すべき資本」とはなんでしょうか?
組織論学者であるリンダグラットンさんは『LIFE SHIFT』にて蓄積すべき個人の無形資産として以下の三つを上げています。
1.生産性資産(スキル・仲間・評判など)
2.活力資産(健康・友人・愛など)
3.変身資産(自己理解・多様な人脈など)
『LIFE SHIFT(ライフ・シフト)』
これら三つ全てあてはまるのが「人的資本」であると私は考えています。
この人的資本、つまり仲間・友人・多様な人脈、これこそ最も時間が必要で人生の早い段階から意識的に行わないといけないと考えています。
職住近接の話に戻ります。
職場に行かなくてよくなったと言います。
リモートワークで問題なく働けると言います。
私もそう思います。
しかし、人的資本は蓄積されるでしょうか?
言葉を変えると、果たしてリモートワーク親密な同僚もしくは信頼できる仲間を構築できますか?
できていると思える同僚は、恐らくリモートワーク前によく顔を合わせていたからです。
会社をやめるつもりであってもこれは同じで、結局今の同僚と良好な関係を作れなければ、中長期的にどんなに自分が力を持っていても機会に恵まれずその力を発揮できない事が多いはずです。
仕事を進めるにはリモートワークは問題ありません。しかし、長期的に自分の資本といえるような仲間・友人・人脈作りはリアルなコミュニケーションが必要です。
従って、私は顔を合わせたコミュニケーションを通じた人的資本の蓄積を行いたいため、オフィスにほとんど行かないことを前提にする地方移住を考えていません。

多分、地方に移住したらオフィスに行くのは億劫になりますからね。
教育環境は重要

また、子供の教育環境を考慮すると、まだ地方移住には踏み切れません。
私の娘は現在1歳で、今後10年の間に小学校入学のイベントを控えています。
そしてその後も中学校、高等学校を控えています。
そういった子供の教育環境、言い換えると教育の選択肢、教育へのアクセスという点において、まだ圧倒的に東京が優位です。
ここでの反論として「いやいや今どき必要な事はオンラインで学べるから」という声が聞こえてきます。著名な塾の講師、つまり教えるのが上手い先生の動画を見せておけば個人の学習速度に応じた学習ができるといわれています。
しかし、果たして本当にそうでしょうか?
私もUdemyやスタディアプリなどを自分で利用していて、その肌感覚として、オンライン学習の改善余地はまだ大きいです。
とりわけインタラクションにおいてです。
わからないなと思ったことを尋ねる、それについて回答を得る、その回答について自分なりに考える、同様の質問を別の人にする。
このプロセスを通じて”学習”になっているものと強く感じますが、現状のオンライン学習のみではこれを補完できません。
また、オンライン通話などの機能を利用してリモートで実施することについても現行のテクノロジーでは、参加者の積極性や場を共有することによる偶発性に限界があるというのを自分自身もリモートワークで感じています。
従って、私は教育環境が不十分な地方に現時点で移住することは考えていません。

この点は5Gのソリューションなどには期待は大きいところですが、向こう5年ぐらいは教育現場への影響は少ないでしょう。
地方の不自由さに変化はない
ジョブメンズラボの地方在住いーとんがそのリアルな生活を書いた記事からも、地方のデメリットがよくわかります。
「車社会」「コミュニティが狭い」という点があげられています。
この点はコロナ禍、コロナ後でも全く変わりません。
デジタルテクノロジーで生きやすい状況になったとはいえます。
しかし、まだテクノロジーの恩恵は実社会の隅々まで行き届いているとはいえません。
私は現在のテクノロジーの普及、もしくはさらに進化したテクノロジー(自動運転、テレプレゼンス、VRなど)が普及してから地方移住をしても良いと思います。
まとめ

今回はMBAである私が東京に住み続け、職住近接を継続する理由を紹介しました。
地方移住という新しい変化の機運に対して否定的な態度をとってしまいましたが、社会の変化の加速は間違いありません。
逆に言うと、私が挙げた点が気にならない方は地方移住ができる方ともいえます。(もしくは移住してみて嫌なら帰ってくれば良いですしね!)
しかし、私はあえて東京住まいを今後も続けていきます(^^)/
皆さんのご意見は是非TwitterのDMで連絡ください!!